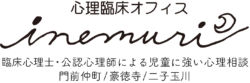2019年11月24日(土)10時~11時半に勉強会を行いました。
当日は現役の声優の方にご参加いただいています。
参加者のみなさま、気にかけてくださったみなさま、ありがとうございます。
今回は「読み聞かせイベントにおける配慮について」がテーマでした。
実際に読み聞かせの場を開いている方のご参加でしたので、実際にお困りのことについて具体的に意見をさせていただきながらの勉強会になりました。
例えば、
乳児さん幼児さん合同のイベントで、(場の構造から)発達障がいのある幼児さんを興奮させてしまうというお悩みについて。
幼児さんが興奮して走り回ったり、大きな声で叫び回ったりされると、中には怖がってしまう乳児さん(どうしたって踏まれそうにもなりますね)も出てきて、イベントの安全を守りきれないとのことでした。
だからといって、その子たちが来れなくなってしまうのは嫌だし……、むしろ来て欲しいし……、とのこと。
単純に考えれば、
・スタッフの数を増やして対応する
(または、てだれの保育士さんに来てもらう)
・幼児の部と乳児の部を分ける
・走り回れる部屋を作って、読み聞かせを聞けるときだけ中に来てもらう
などの解決策が挙げられますが、物理的に難しいとのこと。
お部屋も一つしか使えませんし、時間も限られています。
自由な場であって欲しいという願いもあるそうです。
しかし、お話を伺っていると、いくつかの改善点が見つかりました。
あくまでやってみないとわからないのですが……
まずは、発達障がいの特性について説明。
それから、紹介程度にはなりますがTEACCHプログラムについて、
すぐに取り組めそうな「構造化」についても具体的にお伝えしました。
場所や時間の構造をわかりやすく作ること。
それから、特性への配慮として「事前予告」の大切さ、「はじめ、と、終わり、の明確化」について等々。
そのイベントは定期的に行われているものなのですが、
〔①読み聞かせ〕⇒〔②マットをとっぱらっての自由遊び〕という流れがあるそうです。自由遊びの際は、読み聞かせをしていたのと同じ部屋で走り回り、大きな声を出して戦い、暴れ、スタッフも全力で本気で遊ぶとのこと。
そうなるとどうしても、特に発達障がいのある子どもたちにとっては「ここは走って、暴れて良い場」とインプットされがちです。
彼らにしても「良いときもあるのに、なんで!」と納得がいかないことも推測できます。
ですが、この構造は崩せないとのこと。
ですので、まずは、スタッフの方に、この発達障がい児たちの見え方や理解の仕方、記憶などのクセを理解していただくことからかな、と思っています。
後は、即効性はありませんが、部屋に入る前に「絵本が終わったら遊び。絵本が終わるまで走りません。歩いて過ごします」などとしっかりと伝えてもらうこと。
少しでも走ったら「絵本が終わったら遊び。歩きます」と近くに行って小さな声で淡々と伝えてあげられると良いですね。決して叱責はせずに。
また、後で走って遊べる、と見通しを持ってもらうことは非常に重要です。
もう一つの気になる点は、
受付を済ませてから、開始までの時間についてです。
受付開始時間になると、親子が三々五々集まってきます。はじまるまでは、無法地帯。それぞれが自由に過ごして、大騒ぎの状態だそうです。
★前に来たとき、走り回って遊んだ部屋だ!
★中に入ったら、人も多いし、色々な声もするし、刺激が多いぞ!
★(目の前には)ひろーい場所があるぞー!
★その上、自由時間で何をすればいいかわからないよー!
発達障がいの子どもたちの多くは「やることがない場面」「何をすれば良いかわからない場面」がとても苦手です。その上刺激が多いとなれば、
それは興奮もします。
走りもします。
そして、一度、大興奮で走り出したものを、収めることは非常に困難でしょう。
収める気がないのではなく、収められないのです。
一見、笑顔だったりもして、好きで走っているように見えます。だけれど、本当は笑いたくもないし、走りたくもないのだけれど、脳の命令でそうせざるを得なく、走っている場合もあります。
この場合の配慮としては、
・部屋に入ったら、はじまるまでの間にやるべきことを作っておく。
・手すきのスタッフがいれば、プレ開始のような感じで、何かをはじめておく。来た子から参加できるようにしておく。(例えば、簡単なお遊戯や読み聞かせなど)
・興奮しやすい子が入室したら、すぐに近づいて一緒に静か目の遊びに誘う役目のスタッフを作る
などが、代表的なものとして挙げられます。
暇な時間を作らないであげることが非常に重要になってきます。一旦、興奮したものを抑えるのは非常に大変なので、(読み聞かせにつながるように)興奮しすぎないように配慮します。
スタッフの人数がいないと厳しいのですけどね…
繰り返しになってしまいますが、「本当はこういう配慮があるといいんだ」とスタッフが知っているだけでも違いは出てくると思っています(二つの小さな選択肢があったときに、より、特性にあった選択をスタッフができるようになると思うからです)。
ここに書くのは勉強会でお話したうちの一部です。
このような話を現場や実情に合わせてさせて頂いています。
参加して下さった方には、来ていただいたこと心から感謝しています。
笑顔で走り回っていても、本当は読み聞かせを楽しみたい子どももいるだろうと思いますから、少しでもこういった配慮が広まるように願います。